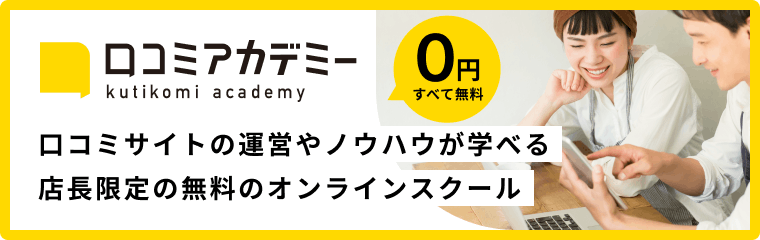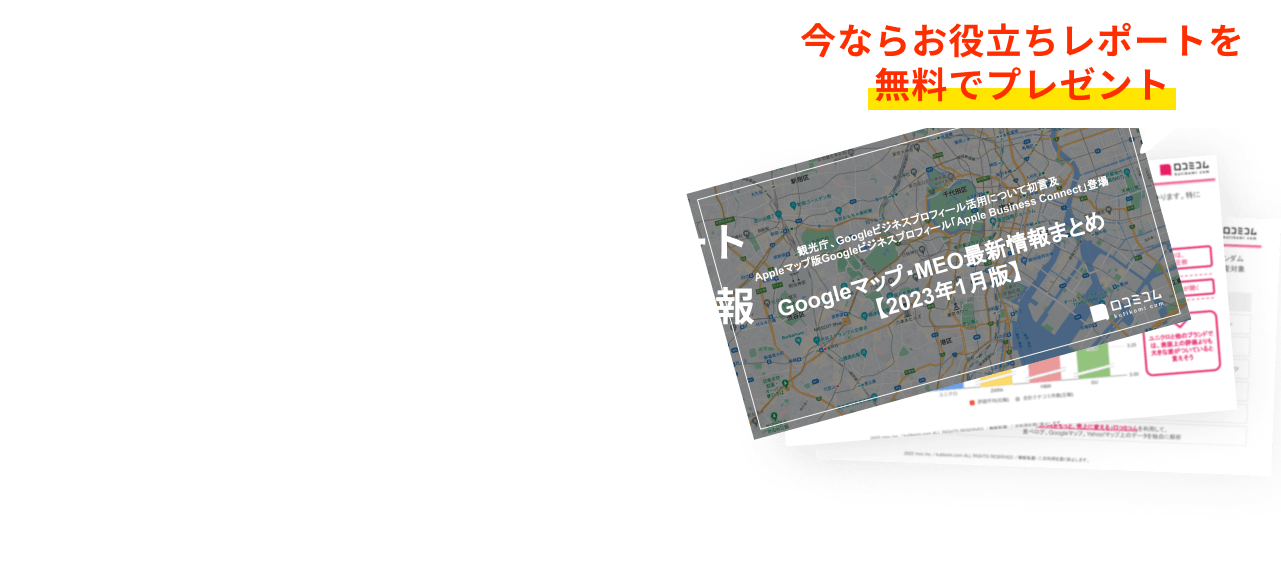マーケティング施策には、人が消費活動の中で意思決定をするにあたってはたらく心理現象を利用したものも多くあります。その一つが最初に提示した値段よりも低い値段を後に提示することで、後に提示された値段が低く感じる効果であるアンカリング効果です。
小売業界で広く用いられる心理効果ではありますが、冠婚葬祭においてもアンカリング効果を活用できます。本記事ではアンカリング効果の概要についてふれながら、具体的な活用例や、活用時の注意点について解説します。
アンカリング効果とは
アンカリング効果は、商品購入の意思決定の際に身近に用いられている心理効果でもあります。消費者が意思決定をする際にどのような心理効果がはたらいているのかを知ることで、マーケティングや販売トークに活かせます。
アンカリング効果とは?意味やマーケティングへの活用事例を業種別に紹介
たとえば2万円の予算で掃除機の購入を考えていたときに、元値が4万円の掃除機が在庫処分のため2万8,000円で売られていたら予算をオーバーしているのにもかかわらず購入を検討してしまうことなどが挙げられます。 この場合、元値の4万円が基準となるため顧客にお得感を感じさせます。
消費者の意思決定に影響を与える心理効果
アンカリング効果は、船がアンカー(錨)をおろすとそこから動かなくなる状態に由来した言葉で、消費者が商品購入などの意思決定において、最初に得た情報や印象に残った情報を元に意思決定をすることを指します。
アンカリング効果がはたらく例として代表的なものが価格です。価格は消費者にとって最もわかりやすい指標であり、消費者が商品やサービスの購入をしようと思ったときに、最初に見た商品の価格がその人の中での基準となります。価格だけでなく商品の情報においても同じことがいえます。
最初に提示する価格や条件を調整することにより、消費者に販売者側の求めている判断をしてもらうこともできるため、販売時にはこのことを意識するとよいといえます。
アンカリング効果を活かした価格表示
アンカリング効果は価格表示で最もその効果を発揮します。マーケティングにおいてよく使われるのが、最初に購入してほしい価格よりも高い価格を提示し、その後低い価格を提示することで消費者に希望額で購入してもらう方法です。
消費者はアンカリング効果がはたらいているため、あとに提示した価格を安いと感じます。
一方で容量や保障年数といった大きい数字の方がメリットが感じられる場合には、逆の手法が使われていることがあります。最初に小さい数字を提示して次に大きい数字を提示する方法です。この方法を使うことで、消費者は後で出された数字をより大きいものとして認識しやすくなります。
価格表示以外のアンカリング効果の活用例
また価格や容量などの具体的な数字以外にも、商品に関連のない数字を用いることでアンカリング効果が発揮されることも証明されています。これは直前に見た数字に無意識にアンカリング効果がはたらくことで起こる現象です。
この現象を応用して、売り場のPOPや商品のパンフレットなどに使われるコピーに大きな数字をさりげなく使うことで、商品に直接関係ない数字であっても、商品の価値が高いと感じさせることもできます。
具体的な数字以外にも、商品やサービスの情報でも同様の効果が期待できます。たとえば商品を提示する前に、使われている技術が質の高いものであることや歴史のある技術を用いて作られていることをアピールするといったケースがあります。
結婚式場や葬儀場でのアンカリング効果の活用例
消費者の意思決定に影響を与えるアンカリング効果ですが、葬儀場や結婚式場においてもアンカリング効果を活用したマーケティングが実施できます。本記事では実際にどのように活用するかについて具体的に3つの活用方法を紹介します。
1. 松竹梅の法則を併用した価格表示
松竹梅の法則とは、値段の違う3つの価格が設定された商品が並んでいるときに、真ん中の商品を購入する人が多くなるという法則です。この法則とアンカリング効果を利用して、最初に「松」の商品を提案し、その後「竹」の商品を提供する方法があります。
結婚式のプランは、披露宴の食事やドレスの種類などで料金が変わります。
たとえば食事の内容を、5,000円のコース、10,000円のコース、15,000円のコースと3つ用意した場合に、最も選ばれやすくなるのは10,000円のコースです。
提案する際には、最初に15,000円のコースを提案してその後10,000円のコースを提案することで、アンカリング効果と松竹梅の法則の影響で、より10,000円のコースを選んでもらいやすくなります。
[blogcard url="https://lab.kutikomi.com/news/marketing/toomanychoices/?utm_source=rss_all"]
2. 顧客満足度や利用者数をアピールする
顧客満足度や利用者数、歴史や伝統などの指標をもとにアピールするのも一つの活用方法です。
たとえば結婚式場を選ぶ際に、口コミなどで評価や満足度の高い式場であれば挙式の費用が高くとも、式場の価値に納得して契約してもらえます。冒頭に解説したように、具体的な数字でなくとも商品が持つ価値について顧客に伝えることで、価格交渉以外の部分でもアンカー効果を活用できます。
さらに結婚式や葬儀のようなイベントは、人生に何度も起こるイベントではありません。そのため多くの人が、「思い出に残るように」、「故人のために」と顧客満足度の高い会場や、利用者の多い会場を選ぶ傾向にあるため、これらのアピールが有効に作用します。
3. 価格でなく店舗の内装で他店との差別化をする
価格や伝統以外の部分で他店との差別化を図る方法もあります。顧客が来店した際に第一印象として残るのが店舗の内装です。
たとえばブランド物を取り扱っている店舗で、入店してすぐの場所に高級な商品を目立つようにディスプレイしていることがあります。これは来店時の印象を「高級店だ」という認識にするための手法です。
結婚式場であれば、高級感のある内装を施すことで、シンプルな内装の式場と比べると、「この式場は高級感がある」という印象を与えられるため、たとえ結婚式のプランの価格が高くとも、納得して購入してもらえます。商品を販売する際には、商品の価格や内容、セールストークに着目されがちですが、それ以外の部分でもアピールできます。
[blogcard url="https://lab.kutikomi.com/news/retail/behavioraleconomics287/?utm_source=rss_all"]
アンカリング効果を冠婚葬祭で活用する際の注意点
活用することのメリットも多いアンカリング効果ですが、活用方法を間違えると企業の印象を悪くしてしまったり法律に反してしまう可能性もあります。アンカリング効果の活用の際に気を付けなければいけない点について2つの側面から注意点を解説します。
1. 二重価格表示をしない
二重価格表示とは、セール時などに通常販売価格を引き上げ、割引後の価格が通常価格と実質変わらないような値段設定をすることでアンカリング効果を狙い、お得さを感じさせる方法です。二重価格表示は顧客からの印象が悪くなるだけでなく、景品表示法に違反しています。
実際にアンカリング効果を狙い通常価格とセール価格を比較して情報を発信する際には、セール開始時から過去8週間の中で4週間以上通常価格で販売していた実績が必要です。8週間に満たない場合でも、商品を販売していた期間の過半かつ2週間以上の実績がなければなりません。
その他の例など、詳しくは消費者庁のサイトで確認しておきましょう。
2. 偽りの情報を発信しない
顧客満足度や利用者数をアンカリング効果の活用例として利用できることについて紹介しましたが、この時に用いる数字を水増ししたり、提示する金額を変えることは顧客からの信頼を失うことにつながります。
たとえば葬儀プランに「表示価格以外の料金はいただきません。」と記載しているにもかかわらず、請求時に追加料金が上乗せされている場合です。
たとえ請求した金額がプランの追加などによる正当な金額であっても、顧客は表示されている以外の料金はかからないと思っているため、信頼度低下の原因となります。
商品やサービスを説明する際には、偽りの情報を伝えないよう、また、顧客が勘違いしてしまう伝え方をしないように注意しなければなりません。
アンカリング効果と顧客への誠実さを両立し、持続的な集客
アンカリング効果とは、消費者が意思決定をする際に集める情報のうち、最初に得た情報が基準となりその後の情報を判断する心理効果です。アンカリング効果が最も活用されているのが価格や商品情報にまつわる数字です。
結婚式や葬儀においてもアンカリング効果が有効です。たとえばプランの価格設定においては、松竹梅の法則とアンカリング効果を組み合わせることで、顧客に最も選んでほしいプランを選択してもらえます。価格だけでなく顧客満足度や利用者数も重要な情報です。
しかしながらアンカリング効果を狙った二重価格表示や偽りの情報発信は、法律違反になったり顧客からの信頼を失うことになったりします。ビジネスにおいては商品を利用する顧客の満足度を忘れずに、アンカリング効果はじめ行動経済学の理論は、あくまで商品の魅力を伝える手段であることを忘れてはならないでしょう。
口コミラボ 最新版MEOまとめ【25年6月版 Googleマップ・MEOまとめ】

そこで口コミラボでは、MEO・口コミマーケティングに役立つ最新ニュースをまとめた「Googleマップ・MEO最新情報まとめ」を毎月発行しています。
本記事では、主に2025年6月の情報をまとめたレポートのダイジェストをお届けします。
※ここでの「MEO」とは、Google上の店舗・施設情報の露出回数を増やしたり、来店行動につなげたりすることで、Google経由の集客を最大化させる施策を指します。
※『口コミアカデミー 』にご登録いただくと、レポートの全容を無料でご確認いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。
→Googleビジネスプロフィールの投稿機能のUIが更新、旧UIとの違いは?:【2025年6月版 Googleマップ・MEOまとめ】